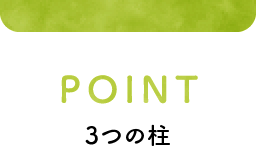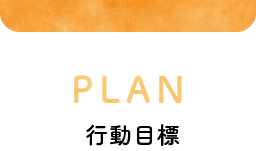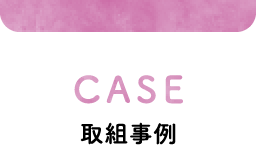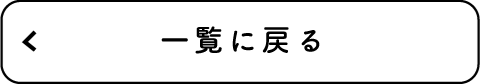[2025.04.28]
環境基金助成金支給団体 活動報告
コープおおいたでは、本部事務所から排出される古紙などや各店舗のリサイクル食品トレー・有料レジ袋の益金を「環境基金」として摘み立て、環境活動や助成事業に取り組んでいます。
大分県内で環境活動に取り組み、3年以上の活動実績のある団体やグループの助成団体を公募し、2024年度は下記の6団体に環境基金助成金を各20万円支給しました。
■団体名「NPO法人 水辺に遊ぶ会」(写真左)
代表者 理事長 足利 慶聖 氏
大分県北部に広がる中津干潟を中心とした水辺環境の保全活動及び自然観察会などを通じて市民にふるさとの自然について関心を深めてもらう活動を行っています。同時に研究活動にも勤しんでおり、中津干潟に生息する底生生物の魚類・野鳥の観察を通して、子どもたちの情操を育み、海での作業(海苔すき)を体験しました。海苔すきを体験することで海苔が食卓にのぼるまでの一端を知ることができ、実際に生産者の声を聞くことで海苔養殖業についての理解が深まりました。これらの活動を通して海の環境の大切さを知り、保全する気持ちを育てることも目的の一つであります。助成金は行事広報の通信費、チラシ代、講師謝礼金などに活用させていただきました。
■団体名「公益社団法人 別府湾をきれいにする会」(写真右)
代表者 理事長 島田 忠 氏
別府湾沿岸の漂流物の除去及び投棄の防止に関する啓発などの事業を行い、湾内水域の美観の保持と公衆衛生の向上並びに漁場環境の保全に資するとともに、船舶航行の安全に寄与することを目的とする活動をしています。子どもたちに清掃船への体験乗船の機会を提供し、海の環境や漂流ごみの回収から処分に至る一連の作業行程を説明するなどの啓発を行っている中で、その際に着用するライフジャケットが20年を経過したため、安全面を考慮し新しいものに更新しました。助成金は、ライフジャケットと海の学習のことを思い出し環境保護の意識啓発につながるよう清掃船のイラストを入れたクリアホルダーに活用させていただきました。


■団体名「大分生物談話会」(写真下段左上)
代表者 瀬口 三樹弘 氏
大分県内の生物・地質に関する調査研究を行い、その成果の普及啓発を目的として会誌を発行しています。あわせて大分の豊かな自然環境を体験できる場として自然観察会も実施し、環境教育の一助としても活動しています。
令和6年には会誌第13号を発刊し、内容を周知するため大分大学で報告会を開催しました。さらに次世代を含め、より多くの方に読んでもらい、社会教育や学校教育でも活用してもらうため、大分県内の図書館や高等学校などに配布。助成金は、「会誌第13号」300部発行のための印刷費に活用しました。
■団体名「別府市上人ヶ浜町自治会」(写真下段右上)
代表者 会長 阿部 修司 氏
別府市上人ヶ浜町の国道10号線上人ヶ浜交差点周辺は、国道と県道の間に位置し、従来はすすき等が生えた荒廃地でした。別府市内への入り口部分で交通量も多いこともあり、行き交う人々を癒す目的としてここに花壇を造ることを目的に平成30年3月に国交省と花壇ボランティア契約を締結しました。本場所は、信号機で停車中の車よりゴミ(たばこの吸い殻。空きペットボトル、紙くずなど)が多くポイ捨てされている現状があります。当初はポイ捨ての抑止文言の看板の設置を予定していたが、柔軟な文言で花壇に親しみを持ってもらうものにしました。助成金は、看板代、小道具、土、肥料などに活用しました。
■団体名「NPO法人 エー・ビー・シー野外教育センター」(写真下段左下)
代表者 藤谷 将誉 氏
青少年健全育成・社会教育の推進・環境教育推進の3つの柱を掲げ活動をしています。幼児期の自然体験の減少と子育て世代(特にママ)の孤立化への問題を背景に小さい頃から大自然の中で生き物と触れ合う経験を通して、自然環境や命を大切にする心を育むことを目的とし、天然のビーチがある海の環境がある自然豊かなフィールドで親子が自然に親しむ機会を提供しています。助成金は講師謝礼や交通費、会場費などに活用いたしました。
■団体名「妙音山を守る会」(写真下段右下)
代表者 多賀 文雄 氏
当会は、20数年前に大分県が設置した妙音山森林自然公園の放置荒廃の現状をうけ、発足した団体です。自然環境を取り戻すべく設置当初の姿にもどすことを目的として、公園全体の進入竹の駆除、伐採、草刈り等の作業を通じて、失われつつあった地域の交流と活性化を目指してます。助成金は、妙音山森林自然公園の維持管理費として活用いたしました。